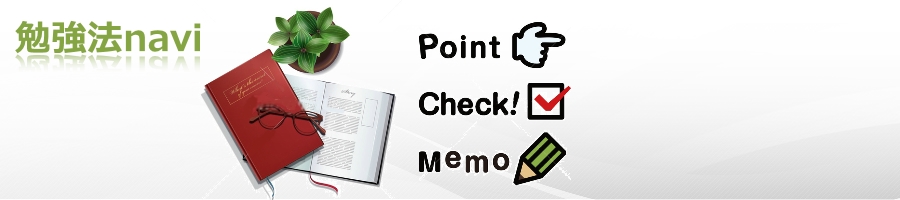
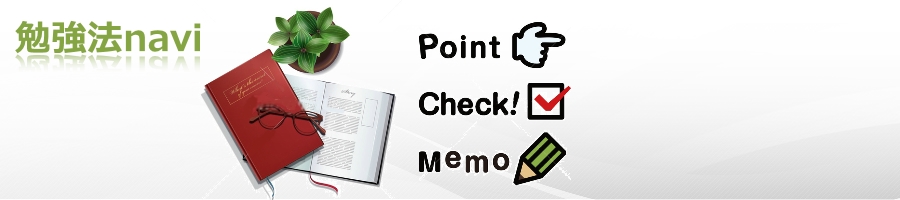
集中のメカニズム

集中するということはどういうことなのでしょうか??
意外なことですが集中力はコントロール可能で、鍛えることもできる力ということがわかってきています。
なんとも抽象的なの力ですが、とても身近なものに代わりはありません。集中力がどのようなものなの知っていれば役立つこともあると思いますので、集中のメカニズムを知っておきましょう。
脳の中で起こっていること
集中しようとする時、脳は2段階の過程を踏んでいると考えられています。特定のものに集中できる能力は、
「トップダウン型注意システム(Top-down attention system)」
と言われています。この方法は自分自身で何に集中したいかを決定する能力のことで、それが決まると、次のような順序で集中していくのです。
①視覚的に入ってくる情報を下に何に注意を向けるかを決定します。
デジカメで風景を撮影する時、何をとろうか全体を見渡して
撮る対象を決めるようなイメージに近いです。
②対象物の一部に注意を向けます。
撮る対象を決めたら、それにカメラを向けズームしていく
イメージということになります。
私たちは集中すると、周囲の事が気にならなくなってきます。この状態はフロー状態と呼ばれていて、周りの声が聞こえなくなるという経験は誰もがあること思います。私たちがこの状態にあるとき、右脳と左脳の両方が、効率的に動いていて、周囲の情報をシャットアウトしています。
この時、時間に対する感覚がなくなり、何かに対して夢中になっている状態に似ていると考えられていますが、実際に、勉強していたり、スポーツをしている人に検査をする事は難しく、詳しいことは確認できていないようです。
集中が途切れるときに脳の中で起こっていること
集中する能力を「トップダウン型注意システム」と言うのに対し途切れていまう状態を
「ボトムアップ型注意システム」と言います。ボトムアップ型注意システムは自身でコントロールできるものではなく、周囲の環境に影響を受けるものです。
このシステムは周囲の状況によって「何に注意を向ける必要があるか?」という判断をするシステムです。集中が途切れる原因は2つあります。
①目立つ色・明るい光を見たとき
②もうひとつは大きな音を聞いたとき
救急車を見たときや、犬の鳴き声などがそれにあたります。日常生活で言えば、何か物を落とした音もそうですね。音や光で強い刺激を受けてしまうと、一瞬でそちらに気がいってしまうということですね。大きな音や、ビックリするような光を目にした時にそれを気にするなと言うのは無理な話です。条件反射的に反応してしまいます。
一旦、集中力が切れてしますと、もう一度集中しなおすのに平均25分かかると言われています。
一旦途切れる度に、もう一度集中するために脳を使いますので、それだけ疲れてしまうことになってしまいます。
ですので、勉強で集中力を持続させるためにはやはり突発的に大きな音が出ない所のほうが、良いということになります。
こちらの記事を書いている今も夜中2:00ですが、とても静かで、集中できます。聞こえる音と言えば食洗機の音くらいです(笑)
集中力とは
 集中するということはどういうことなのでしょうか??意外なことですが集中力はコントロール可能で、鍛えることもできる力ということがわかってきています。なんとも抽象的なの力ですが、とても身近なものに代わりはありません。集中力がどのようなものなの知っていれば役立つこともあると思いますので、集中のメカニズムを...
集中するということはどういうことなのでしょうか??意外なことですが集中力はコントロール可能で、鍛えることもできる力ということがわかってきています。なんとも抽象的なの力ですが、とても身近なものに代わりはありません。集中力がどのようなものなの知っていれば役立つこともあると思いますので、集中のメカニズムを...
限界はどこか
 限界はどこなのか?集中のメカニズムでは、集中している状態から、途切れてしまう瞬間の内容を説明しましたが、今回はその限界について考えていきたいと思います。試験前、今詰めて何時間も何時間も勉強をすると、少し休憩して頭を休めた方が良いと思われることでしょう。休憩に自分の好きなことをしてみたり、テレビを見た...
限界はどこなのか?集中のメカニズムでは、集中している状態から、途切れてしまう瞬間の内容を説明しましたが、今回はその限界について考えていきたいと思います。試験前、今詰めて何時間も何時間も勉強をすると、少し休憩して頭を休めた方が良いと思われることでしょう。休憩に自分の好きなことをしてみたり、テレビを見た...
集中力の回復
 先の話で、集中力は自分次第でどうにでもなる!!と紹介したばかりですが、どうにでもなっても、一度切れてしまったものはやはり回復させる必要があるようです。何かの拍子で切れてしまった集中力、朝からずっと頭が冴えず何事にも集中できない時はやはりあるもの。そこで回復させる為に必要な方法を紹介します。集中力でき...
先の話で、集中力は自分次第でどうにでもなる!!と紹介したばかりですが、どうにでもなっても、一度切れてしまったものはやはり回復させる必要があるようです。何かの拍子で切れてしまった集中力、朝からずっと頭が冴えず何事にも集中できない時はやはりあるもの。そこで回復させる為に必要な方法を紹介します。集中力でき...
